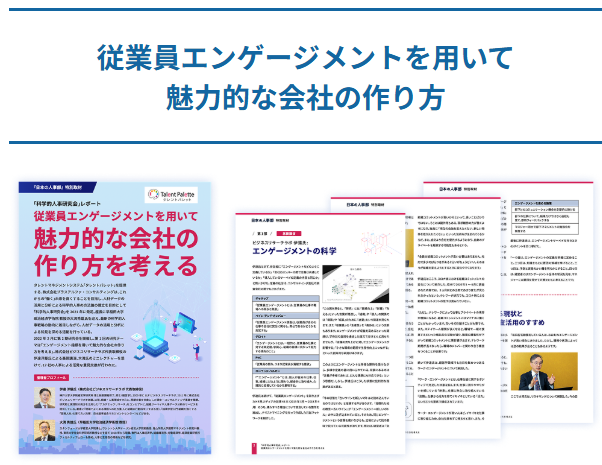こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
少子高齢化の影響で多くの企業が人材確保の悩みを抱えています。企業の人事担当者にとって従業員の定着率の向上は、大きな課題の1つといえるでしょう。ES調査を実施すると、従業員の仕事に対する満足度が分かります。しっかりと対策を講じて、定着率のアップにつなげましょう。
今回は、ES調査を実施するメリットや注意点などを分かりやすく解説します。ES調査のやり方・分析方法・手順、ツールの選び方も解説するので、ES調査の実施を検討している人事担当者はぜひ参考にしてください。
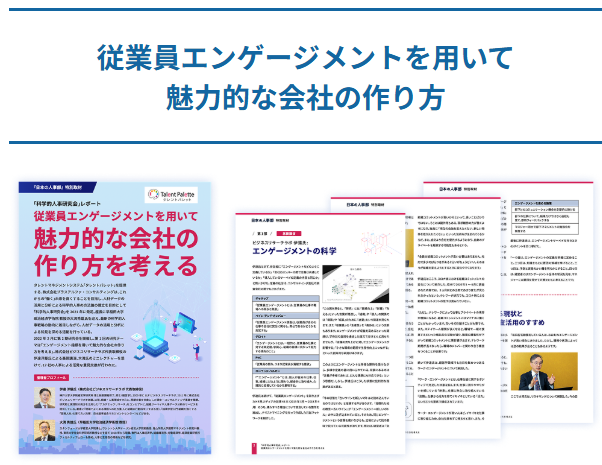
ES調査(従業員満足度調査)とは何?
ES調査とは「Employee Satisfaction」の略称であり、従業員満足度調査と訳されます。従業員に対して実施する調査の1つで、所属している企業に対する従業員の満足度を把握することが目的です。
報酬や福利厚生、仕事に対する満足度や上司・同僚との人間関係など、様々な側面についての設問で構成されています。ES調査の結果は、組織の管理者や人事部門などの関係者に提供され、組織改革や経営戦略の策定などに役立てられます。
ES調査によって従業員の声が届けられ、適切な改善策が取られることにより、自社の職場環境がよりよいものになっていくでしょう。
CS調査(顧客満足度調査)と相関関係がある
CS調査(顧客満足度調査)とは、「Customer Satisfaction」の略称であり、商品やサービスを利用した顧客の満足感や達成感を測る調査です。CS調査では調査対象が企業の顧客であることが、ES調査との違いです。ESとCSには相関関係があり、ESが上がるとCSが上がり、その結果企業の業績が上がる傾向があります。
ES調査とエンゲージメントサーベイの違い
エンゲージメントサーベイとは、企業と従業員の間にある相互理解や相思相愛の度合いの調査です。上司と部下との関係性や経営理念の浸透度合いなど、双方向的な状態を把握するために行います。ES調査はエンゲージメントサーベイとは違い、企業に対する一方向的な満足度を対象に調査します。
ES調査とパルスサーベイの違い
パルスサーベイとは、短期間で従業員の満足度を調査するものです。週1回や月1回などの周期で、小規模・部署単位を対象に、やる気やモチベーションなどを調査します。ES調査は、半年に1回や年1回の周期で、大規模・全社単位に調査を行います。調査の対象は、仕事や職場の満足度や待遇などです。
ES調査が重要視されている理由はなぜ?
ES調査が重要視されるのは、主に3つの理由があります。ここでは、ES調査が重要視される理由について解説します。
離職率を減らすため
ES調査が重要視されている理由は、従業員の離職率を減らして定着率のアップにつながる可能性があるためです。少子高齢化の影響により、多くの企業は人手不足が大きな課題になっています。適切な改善策を取るための手段として、ES調査が重要視されています。
従業員の仕事へのモチベーション向上のため
従業員が離職すると採用や研修など、人事担当者の負担が増えます。結果として生産性の低下や、経済的損失をもたらす可能性があるでしょう。企業は離職を減らすためにも、従業員の声を真摯に受け止め、適切な改善策を講じる必要があります。
適切な改善策を実施することで従業員のモチベーションが高まり、仕事に対する意欲やパフォーマンスが向上するでしょう。
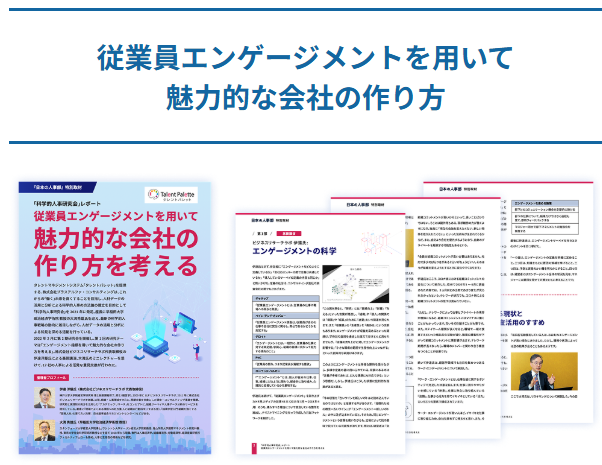
自社に優秀な人材を確保するため
さらにES調査の結果や取り組みを積極的に発信することには、他の求職者に対して企業の魅力をアピールできるという側面もあります。従業員を大切にする企業は求職者にとって魅力的な存在であり、結果として優秀な人材の確保にもつながるでしょう。
ES調査を実施することで得られるメリット・効果
ES調査を実施して適切な改善策を講じると、従業員の満足度が向上して定着率のアップにつながるなど、様々なメリットが得られます。以下では、ES調査を実施することで得られるメリットをいくつかご紹介します。
メリット1:水面下にある組織の課題を早期発見・把握できる
ES調査を実施すると、水面下にある課題を早期発見することが可能です。組織管理者や人事部門は従業員の本音を聞き出すことで、組織内の様々な課題や問題点を把握できます。
ES調査の結果に基づいて必要な対策を講じることで、従業員のモチベーションや企業に対する忠誠心が高まるでしょう。組織内の課題や問題点を把握するためにも、定期的にES調査を行うことは意味あることだといえます。
メリット2:従業員と信頼関係が築ける
従業員と強固な信頼関係を築けるのは、ES調査を実施するメリットの1つです。組織の課題や問題点を解決することで従業員の満足度が向上し、働きやすい環境や待遇を提供できます。
また定期的にES調査を行うことにより、従業員は自分たちが大切にされていると感じるようになるでしょう。より積極的に仕事に取り組み、自己成長や組織の目標達成に向けた努力を惜しみなく行うようになることが期待できます。
メリット3:適切な人事評価を行える
ES調査を通して、優秀な従業員や問題のある従業員を見極めることも可能です。ES調査の結果を参考にすると、客観的で公平な人事評価を行えるため、相応な報酬や昇進の機会を提供できることにつながるでしょう。
適切な報酬や昇進は、従業員のモチベーションや働きがいを向上させる重要な要素の1つです。機会が相応に提供されることで従業員はより一層の努力をし、仕事に取り組むようになります。
メリット4:企業の業績・生産性向上につながる
ES調査によって得られる従業員の声や意見に基づいて、組織内の改善点や課題を解決することは企業の業績向上に寄与します。従業員の満足度や働きやすさを向上させることで、組織全体のパフォーマンスの向上が期待できるためです。
組織全体のパフォーマンスが向上する理由として、労働環境や職場の人間関係を改善することで、チーム内のコミュニケーションや連携が強化されるという点が挙げられます。協力や協調の文化を育むことにつながるため、風通しがよい職場環境づくりにもつながるでしょう。
メリット5:やりがいを可視化し、定量的なデータとして活用できる
従業員のやりがいやモチベーションを可視化できる点もメリットです。面談や日常の観察だけで、従業員が業務や組織について思っていることを把握するのは、容易ではありません。ES調査により定量的なデータを得られ、施策検討の根拠として活用できます。
ES調査が意味ないといわれる理由
ES調査には、目的や心理的安全性などが求められます。ここでは、ES調査が意味がないといわれる理由を解説します。
目的が明確になっていない
ES調査の目的が明確でない場合、従業員は参加する意義やメリットを感じられなくなります。収集する情報や方向性も曖昧になり、調査そのものが目的となるでしょう。ES調査の目的を明確にするためには、具体的な課題を把握したうえで、改善の方向性を決める必要があります。従業員に調査の意義やメリットを伝えることで、質の高い回答が得やすくなります。
心理的安全性が保障されていない
心理的安全性とは、発言や行動に不安を感じない状態のことです。従業員がES調査に対して安心できない場合、率直な回答を得にくくなります。人間関係や人事評価などへの影響を考慮して、無難な回答に偏る可能性があります。心理的安全性を担保することで、自由に意見を得られる工夫が必要です。
フィードバックや改善が不足している
ES調査のフィードバックや改善が不足している場合、意味がないと思われる可能性があります。調査の参加意欲や積極性を失い、不満が溜まりやすくなるため注意が必要です。調査は従業員の時間とエネルギーを費やすため、調査結果や分析結果などのフィードバックが求められます。企業の改善する姿勢がみられない場合、従業員の不信感や疑念につながります。
データを分析できていない
データの分析ができない場合、正確な調査結果は得られません。定量的な数値のみを分析すると実態と異なる結論につながるため、注意しましょう。平均値のみに注目することも、従業員の不満が埋もれる原因となります。平均の点数だけでなく回答の分布もチェックして、不満をもつ従業員の意見に耳を傾けることが大事です。
ES調査を実施する際の注意点
ES調査にはメリットがある一方で、実施時の注意点も存在します。適切な方法で実施しないと目的の達成につながらず、時間と手間の無駄に終わってしまうでしょう。以下では、ES調査を実施する際の注意点について解説します。
構成・構造を工夫する
ES調査の質問項目やフォーマットは、従業員の意見や声を的確に把握するために重要です。適切な質問項目や回答形式を選ぶことで有益な情報を収集できます。
設問数が多すぎると後半の回答が適当になる可能性があるため、質問項目を絞ることが大切です。ES調査の目的を明確に定め、従業員の満足度や組織文化、職場環境など、把握したい情報に合わせて項目を選定します。また、匿名性を保証することも大切なことの1つです。従業員が自由に意見を述べやすくなるでしょう。
定期的に実施する
ES調査を定期的に実施することは、PDCAサイクルを回転させるうえで重要な要素です。定期的な実施・比較によって、従業員の心境の変化や傾向を継続的に把握できます。
従業員から継続的なフィードバックを得ることで、改善策の効果を測定し、必要な調整を行えるようになるでしょう。
形だけのES調査にせず継続する
ES調査は単なる形式的な手続きにとどまらず、その結果を真摯に受け止め、実際の改善策に反映させることが重要です。従業員の声に真剣に向き合い具体的な行動を起こすことで、従業員との信頼関係を築けます。
また改善の取り組みは一度だけではなく、継続して行うことが重要です。ES調査の結果をもとに改善策を実施し、その効果を評価、さらなる改善を行うサイクルを継続させることで、抜本的な問題解決や組織の持続的な成長を実現できます。
ES調査の管理だけで終わらない、あらゆる人事データを統合して分析
ES調査で得られた情報を「管理」するだけでなく、人材情報を「活用」するには、タレントマネジメントシステム『タレントパレット』がおすすめです。
以下の機能により、様々な経営課題と向き合えます。
- あらゆる人事情報を一元集約
- 人材の見える化で埋もれた人材を発掘
- AIシミュレーションで最適配置を実現
- 簡単操作で高度な人事分析が可能

ES調査のやり方・分析方法・手順とは
ES調査はPDCAサイクルを回すことが重要です。PDCAサイクルを効果的に回すためには、一定のステップを踏んで実施しなければなりません。以下ではES調査の具体的な準備・やり方について順を追って詳しくご紹介します。
1:目的を明確化する
ES調査の目的を明確化することは、調査項目設計をスムーズに進めるうえで非常に重要です。目的を明確に定義することで、必要な情報を収集するための質問項目を適切に設計できます。
反対に目的が曖昧なまま調査項目を設計してしまうと、必要な情報が抜け落ちたり、不適切な質問が含まれたりする可能性があるでしょう。
2:質問項目を設計する
次に、調査の対象や目的に応じて、適切な質問項目を設計します。質問は曖昧さを排除し、従業員が明確に理解できる形式でなければなりません。抽象的な表現は避け、具体的で明解な内容にすることを心がけましょう。
3:従業員に回答を依頼する
質問項目を設計できれば、設計した質問項目をもとに従業員に回答を依頼します。回答方法や期限などを明確に伝え、従業員が参加しやすい環境を整えることが重要です。
従業員に回答を依頼する際は、事前に調査目的や概要などを説明しておきましょう。従業員の利益につながることを訴求することにより、回答率アップが期待できます。
4:アンケート結果を集計・分析する
従業員から回答を得られたら、次は回答の集計・分析を行いましょう。集計・分析方法として「単純集計」「クロス集計」「満足度構造分析」などがあります。
単純集計
単純集計とは質問項目ごとに回答の数や割合を計算し、集計結果をまとめる方法です。回答の分布や傾向を把握するのに役立ち、分析の基礎的な数値を把握できます。集計結果をグラフなどで視覚化することで、データの特徴やパターンの把握が容易になるでしょう。
クロス集計
クロス集計とは複数の質問項目を組み合わせてデータを分析し、関連性や相関関係を調べる方法です。具体的には性別と満足度の関係や、部署と意見の関連性などを分析できます。
満足度構造分析
満足度構造分析とは複数の質問項目を組み合わせて、満足度の構造を解明するための統計的手法です。従業員の総合満足度が高い場合、それは単一の項目だけでなく、複数の項目が相関関係を持って高い満足度を形成している可能性があります。
項目ごとの相関関係を分析することで、従業員の満足度がどのような構造やパターンで形成されているのかを明らかにすることが可能です。これらの集計・分析により、従業員の満足度を高めるためのデータを収集できます。
5:対策を検討・考案・準備し、経営層には報告、従業員にはフィードバックを行う
データの分析結果に基づき適切な対策を考案できれば、経営層には報告・従業員にはフィードバックを行います。
経営層への報告では、よかった点と悪かった点の分析結果を中心に報告するのが効果的です。よかった点については評価し、継続・強化すべき点として報告します。
一方で、悪かった点や改善が必要な課題については、その原因や具体的な対策案を示し、経営層と共に取り組むべき方向性を提案します。
従業員へのフィードバックでは、全体的な傾向や結果をおおまかに伝えることが重要です。従業員は自身の回答が匿名であることを前提に回答しているため、具体的な個人の回答内容を明示することは避けるべきといえます。従業員は自身の声が反映されていると感じることにより、企業に対しての信頼感が高まるでしょう。
6:対策を実行する
経営層の了承が得られると、考案した対策を実行し改善を実現します。対策を実行する際は、従業員とのコミュニケーションを密にし、対策の進捗状況や結果を共有することが重要です。
なお対策実行に関しては、ES調査から期間を空けすぎないよう注意しましょう。従業員の心境や状況は時間とともに変化するため、対策の実行が遅れると調査結果が現実と乖離してしまう可能性があります。
ES調査の設問項目の例
ES調査を実施する際は、適切な質問項目の設計が欠かせません。質問項目は従業員の声や意見を的確に収集するために必要な要素といえます。以下では、質問項目の具体例をご紹介します。質問項目を設計する際の参考にしてください。
従業員の属性が分かるような項目
従業員の属性に関する項目は、従業員の個人情報や基本的な特徴を把握するための項目です。年齢、性別、職位、勤続年数などが質問項目になります。
ES調査は原則匿名で実施するものですが、後々の分析のためにも、ある程度属性が分かるような項目を入れることが必要です。従業員のプライバシーを保護しつつ、基本的な情報を収集しましょう。
業務に関する項目
業務に関する項目は、従業員の業務内容や業務遂行に関する状況、課題について質問する項目です。従業員の業務に対する満足度や、やりがいの程度を把握することを目的とします。
具体的な質問としては「現在の業務内容は自分に合っているか」「仕事にやりがいや意義を感じているか」「業務上の課題や改善すべき点は何か」などが挙げられるでしょう。
職場環境に関する項目
職場環境に関する項目は、従業員が働く環境や労働条件、人間関係などについて評価する項目です。従業員の働きやすさや職場の魅力、ストレス要因などの把握を目的とします。
質問の具体例としては「業務の手伝いを依頼しやすいか」「一人当たりの仕事量は適切か」「職場の雰囲気は良好か」「労働時間や休暇制度は満足しているか」などが挙げられるでしょう。
評価に関する項目
評価に関する項目は、従業員の業績評価や報酬、昇進などに関する項目です。従業員が自身の成果や評価に対して、どのような意見や感想を持っているのかなどの把握を目的とします。
具体的な質問としては「人事評価は適切に行われていると感じるか」「自身の成果に対する評価は公平か」「報酬や昇進の制度に満足しているか」などが挙げられるでしょう。
上司に関する項目
上司に関する項目は、従業員と上司の関係や上司の行動に焦点を当てた項目です。上司とのコミュニケーションや指導、サポートの質などについての把握を目的とします。
具体的な質問としては「上司はフォローしてくれるか」「上司からの指示は的確か」「上司は問題解決や困難に対して適切な支援をしてくれるか」などが挙げられるでしょう。
経営に関する項目
経営に関する項目は、組織の経営層や経営方針に関連する質問を含む項目です。組織のビジョンや方針、意思決定プロセスなどについて従業員の評価や意見の収集を目的とします。
具体的な質問としては「経営層は魅力的なビジョンを発信しているか」「経営層は従業員を信頼してくれていると感じるか」「組織の意思決定プロセスは公正か」などが挙げられるでしょう。
総合的な項目
総合的な項目は、企業、職場、業務への満足度を総合的に把握する項目です。具体的な質問としては、「今後も当社で働きたいか」「総合的にどの程度満足しているか」などが挙げられます。
ES調査のツールを導入するメリット
ES調査のツールの活用により、課題の発見や環境の改善などが可能です。ここでは、ツールを導入するメリットを解説します。
自社の課題を早期に発見できる
ES調査のツールによって、見えにくい自社の課題を早期に発見できます。従業員が抱え込んでいる本音は、面談をはじめとした方法のみでは把握できません。人事や人間関係などに不満があっても、報告できないケースが多くあります。ツールを活用して顕在化していないリスクを洗い出すことで、事前の対策が可能です。
職場環境の改善によって離職率が減少する
ES調査のツールの活用で、従業員の離職率が減少します。調査結果をもとに、職場環境の課題の発見につなげ、人事制度や人事評価制度の見直し・整備ができるためです。課題の改善によって、よりよい職場環境の構築が可能です。また、優秀な人材が定着しやすくなる効果も期待できます。人材の定着によって、採用コストや教育コストなども抑えられます。
タレントマネジメントにも活用できる
タレントマネジメントとは、人材データを一元管理し、人材育成や評価などに役立てる手法です。ツールのアンケートやサーベイ機能などによって、調査の効率化もできます。調査に特化したツールは、質問項目の設計から分析の自動化にも対応しているのが特徴です。ES調査をタレントマネジメントに活用することで、適材適所の人材配置につなげられます。
ES調査のツールを導入する際のポイント
ES調査のツールは、目的によって選び方が異なります。ここでは、導入する際のポイントを解説します。
目的にあった調査ができる
ES調査のツールを導入する際は、自社の目的を達成できるものを選びましょう。たとえば、従業員の満足度の向上や離職防止などです。企業によって目的が異なるため、課題から逆算して決めることが大事です。課題がわからない場合は、現状を多角的に把握・分析できるツールの活用がおすすめです。
ツールが使いやすいかどうか
ES調査のツールは、従業員にとって使いやすいものが必要です。たとえば、アンケートを実施する際、操作性の高いツールであれば回答を得やすくなります。調査方法や回答フォームなどが、従業員に寄り添っているかどうかを確認しましょう。カスタマイズ性の高さも考慮して、問題や課題に対して柔軟に対応することが大事です。
導入実績が豊富にある
導入実績が豊富なツールは、ツールの質や精度が高い傾向にあります。質の高いツールを提供するサービスは、会社の独自調査を行い、データを更新し続けているためです。機能のアップデートをしているため、ホームページで事業者の導入実績を確認して、質の高いES調査のツールを選びましょう。
まとめ
ES調査を定期的に実施してPDCAサイクルを回すと、従業員の定着率の向上につながる可能性があります。なお実施する際は目的に応じた適切な質問項目の設計が必要であり、難しく感じている担当者の人もいるでしょう。
ES調査のツールを活用すると、アンケートやサーベイ機能などを活用して調査の効率化が可能になります。自社の課題を早期に発見し、見えにくい問題や顕在化していないリスクを洗い出して、事前の対策ができるのでおすすめです。ES調査だけでなく、適材適所の人材配置にも活用する場合は、タレントマネジメントシステムの導入を検討しましょう。
タレントパレットを導入すると、自由な設問設定で従業員向けのアンケートを簡単に作成できます。従業員満足度やエンゲージメントを測定して、リアルタイムで集計可能です。興味ある人は、ぜひ以下のリンクをチェックしてみてください。