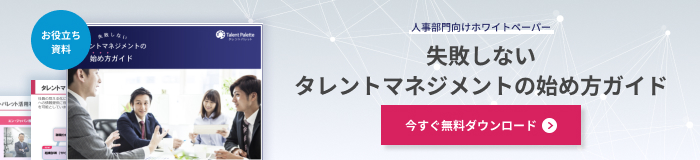人材管理とは?目的も解説
企業の成長や変革を実現するために、経営資源の中でも特に重要とされるのが「ヒト」です。社員の能力やモチベーションを引き出すことで企業の競争力を高め、変化の激しい社会環境に適応できる強い組織作りにつながります。この章では、人材管理の基本的な考え方と目的について解説します。
人材管理の定義
人材管理とは、経営戦略の目標達成のために経営資源の一つ「ヒト」を最大限活用する取り組みです。「人材マネジメント」とも呼ばれ、企業が継続的に成果を生み出すために重要な要素となります。具体的な取り組みとしては、以下のような要素が含まれます。
- 採用:企業のニーズに合った人材を戦略的に獲得する
- 育成:社員の能力開発やキャリア形成を支援する
- 配置:適材適所の原則に基づき、最も効果的なポジションに人材を配置する
- 人事評価:個人の成果や貢献を正しく評価し、処遇や昇進に反映させる
人材を確保して育成し、定着・活用することは企業の競争優位性を支える根幹であり、組織の成長や変革を実現する原動力となります。
人材管理を行う目的
人材管理の目的は経営資源のひとつである「ヒト」を戦略的に活用・育成することで、企業の競争力を強化して持続可能な成長を実現することです。経営の三大資源である「ヒト・モノ・カネ」の中でも、唯一感情や意欲を持って創造的な価値を生み出せるのが「ヒト」です。社員一人ひとりの能力や可能性を引き出し、適切に育成・評価・配置することでモチベーションの向上と職場への定着を促せます。
結果として組織全体のパフォーマンスが向上し、他社との差別化を図ると同時に自社の市場価値やブランド力の強化にもつながるでしょう。また近年は顧客の価値観やニーズの多様化、さらにはテクノロジーの進化など企業を取り巻く環境は複雑化しています。こうした変化に柔軟に対応し、持続的に成果を上げるためには、組織の中核を担う「ヒト」の力を最大限に引き出す必要があります。人材管理を通じて適応力のある組織体制を整備することは、経営の安定化にも直結する重要な取り組みです。
人材管理の5つの業務内容
人材管理を構成する主要な5つの業務は、以下のとおりです。
- 人材の採用
- 人材の育成
- 適切な人材の配置と異動
- 人材の評価
- 能力に見合う待遇や報酬額の決定
上記の業務はそれぞれが独立して存在するのではなく、相互に連携しながら社員のモチベーション向上や組織パフォーマンスの最大化を実現します。この章では、それぞれの業務がどのような役割を担っているかを解説します。
人材の採用
人材管理は「自社にとって必要な人材を的確に採用すること」から始まります。採用は単に人手を補う作業ではなく、将来の組織の成長や競争力を左右する重要な戦略活動の一つです。まずは、自社が必要とする人物像を明確にします。採用要件を明確化する際は求めるスキルや経験だけでなく、組織文化に適応できるかや価値観が一致しているかといった「人物面」も含めて、総合的に定義していくことが大切です。
また既存社員では補いきれない専門スキルや経験を持つ人材を外部から確保することも、採用活動の大きな目的です。新たな視点や価値を社内にもたらすことができる人材を採用することで、組織の機能を強化し、イノベーションを促進することが可能となります。
人材の育成
採用した人材が十分に力を発揮し、組織全体の生産性や競争力向上につながるようにするためには「人材の育成」が不可欠です。具体的な育成手法には、以下のような方法があります。
- 集合研修
- OJT
- e-ラーニング
- 外部セミナー
業務の現場で学ぶOJTは、実践力を高める上で有効です。eラーニングは場所や時間にとらわれず学べる柔軟な手段として、近年多くの企業で導入が進んでいます。さまざまな手法を組み合わせることで学習効果を高めるとともに、多様な人材のニーズにも対応できます。また現時点でスキルや知識が不足している社員であっても、適切な育成機会を与えることで将来的に業績に大きく貢献できる人材へと成長させることが可能です。人材育成は目先の業務遂行力を高めるだけでなく、長期的な人材価値の向上と組織の成長基盤作りを支える取り組みです。
適切な人材の配置と異動
人材の持つスキルや経験を最大限に引き出すためには、適材適所の考え方に基づいた配置と柔軟な異動の仕組みが欠かせません。まずは採用時や育成過程で把握した人材の能力・スキル・適性をもとに、最も力を発揮できる業務やポジションに配置しましょう。適切な配置が行われることで社員は自らの強みを活かして高いパフォーマンスを発揮でき、業務への満足度やモチベーションも高まりやすくなります。
社員が業務を通じて新たなスキルを身に付けたり、資格取得や研修によって専門性を高めたりした場合には、獲得した能力をより効果的に活かすための「配置転換」も有効です。適切なタイミングで異動を行うことで、人材の成長を促進すると同時に組織の中での最適な人材活用が実現できます。「適切な配置と異動」は人材の潜在力を引き出し、個人と組織双方の成長を促す戦略的な人材活用につながります。
人材の評価
人材管理における「評価」は単なる業績の確認にとどまらず、社員のやる気や成長意欲を引き出す重要な役割を持っています。適正な評価が行われることで社員は自らの努力や成果が正しく認められていると実感でき、仕事に対するモチベーションが高まります。評価が曖昧で不公平だと感じられると社員の不満や不信感が高まり、離職やパフォーマンスの低下といったリスクにもつながるため透明性・公平性のある評価制度の構築が不可欠です。また評価のフィードバックを通じて、上司と部下のコミュニケーションを深めることも大切です。期待されている役割や今後の課題が共有されることで、社員は明確な目標に向けて主体的に行動できるようになります。
能力に見合う待遇や報酬額の決定
高い評価を得ていたとしても、報酬が見合っていないと感じる社員は不満を抱きやすいです。待遇への納得感が低ければ、人材の流出につながる恐れがあります。離職を防ぐためには月給や賞与、さらにはインセンティブなどを含む報酬体系を業績評価や貢献度に応じた明確かつ公平な設定が必要です。「成果を出せば報われる」という実感を持てる仕組みを構築することで、組織に対する信頼が深まり、社員の継続的な成長意欲やパフォーマンス向上にもつながります。
また定期的に報酬体系を見直し、市場相場や自社の評価制度との整合性をチェックすることも、優秀な人材に長く活躍してもらうための重要な取り組みです。能力に見合った待遇と報酬の設定は人材の維持・定着のみならず、企業としての魅力や競争力を高める上でも欠かせない戦略的な要素となります。
人事や労務との違い
一般的な人事・労務と人材管理の違いは、経営戦略とリンクしているか否かにあります。一般的な人事と労務の主な業務内容は、以下のとおりです。
- 人事:人事評価、人事異動
- 労務:福利厚生、コンプライアンス、給与計算、就業規則、労働安全衛生など
人材管理は、経営戦略に基づく人材戦略です。一方、従来型の人事や労務はバックオフィス業務ともいわれ、多くの場合は経営戦略と直接リンクしていません。
人材管理が注目されている理由
人材管理が注目される一番の理由は、急激に変化する社会情勢への対応が企業に求められているためです。日本企業は、グローバル化、デジタル化、少子高齢化、コロナ禍などの大きな変化の波に直面しています。大企業も例外ではなく、波を乗り越えられなければ優位性を失うおそれすらあります。
企業が生き残るためには、その時々の経営戦略にあわせて柔軟に人材を確保・配置し、各人の能力を最大限に活用しなければなりません。さらに、働き手の多様なニーズに対応できる職場づくりによって、他社との差別化と人材の定着を狙います。
人材管理のメリット5選
人材管理の実現で得られる5つのメリットを解説します。
企業の組織力が上がる
人材管理では、企業理念やビジョン、経営戦略を全社で共有し、企業と社員が同じ目標に向かって共に成長する視点が重要です。
適切な人材管理ができれば社員の結束が強まり、企業の組織力が向上します。タスクの優先順位や行動基準が明確になり、効率的・効果的な業務遂行が可能になる点も見逃せません。働きやすい職場の実現は企業のイメージアップにつながり、採用活動にも好影響をもたらします。
人材の発掘・育成が効率的になる
企業の人的資源を正確に把握していれば、経営戦略に必要な人材を社内から発掘でき、効率的に育成できます。採用すべき人材が明確になる点もメリットです。新卒・中途採用・年齢・性別・国籍に関わらず、必要な時期に必要な役割を果たせる人材を臨機応変に採用しましょう。経営戦略に沿った採用を実現するためには、人事部のみではなくトップやマネジメント層が積極的に人材管理に関与する必要があります。
社員のモチベーションが上がる
人材管理では、人材戦略を経営戦略の要と捉えて「ヒト」に投資します。具体的には、以下のような施策が必要です。
- 学び直しやスキルアップを支援
- 本人のスキルや希望を考慮した配置
- 功績に応じた公正な評価
社員にとっては自分の進むべき方向性が明確になり、貢献すれば認められて確実に報酬につながる点が魅力です。結果的に社員の自主性や向上心がアップし、モチベーションの維持にも役立ちます。コミュニケーションが活性化するため、革新的なアイデアが生まれやすくなるメリットも得られます。
関連記事:モチベーション向上に有効な施策とは?重要性や低下する原因、測定方法なども解説
社員のエンゲージメントが上がる
エンゲージメントとは、企業に対する愛着心や自発的な貢献意欲です。愛社精神と似た概念ですが、企業に対する社員の一方的な貢献心ではありません。企業の成長と自分の成長が一致する相互の関係性を意味します。
貢献度に応じて適切に評価される仕組みがあれば、社員のエンゲージメントが上がります。企業の成長が自分の成長につながり、主体的に経営戦略の目標実現に貢献しようとする気持ちが高まるためです。
関連記事:社員のエンゲージメントを高めるための具体的な方法9選|成功のポイントも解説
離職率が低下する
エンゲージメントの向上は、離職率の低下にも有効です。優秀な人材が転職を選ぶ理由の一つに、スキルアップ・キャリアアップがあります。しかし、職場がいきいきと働ける場所で適切に評価され、自分の目標を実現できる見通しもあるなら、リスクのある転職を選ぶ必要性が低下します。
関連記事:離職率の改善のためにできることは?離職の原因や改善する方法を解説
人材管理を効果的に行う5つのプロセス
人材管理を効果的に行うポイントは、目標設定・計画立案→実行→評価→改善のPDCAサイクルを繰り返し実施することです。以下で、それぞれのプロセスを詳しく解説します。
1.目標を明確に把握する
人材管理の目標を明確にするプロセスです。経営戦略の目標を明確化して課題を共有し、課題解決に向けて下記の目標を設定します。
- 企業・事業部が達成すべき目標
- 部署・チームが達成すべき目標
- 社員個人が達成すべき目標
目標達成までの期間設定や達成度を評価するための数値的指標も必要です。個々の目標には必ず経営戦略の実現につながる課題を設定し、同じゴールを目指します。
2.自社に必要な人材を把握する
目標達成に必要な人材を把握するプロセスです。企業に所属しているすべての人材のパフォーマンスレベルや、スキルを洗い出しましょう。さらに、現状と目標を比較して、差異を明確化します。目標達成に貢献できる人材が自社にいないと判明すれば、新たに採用しなければなりません。
一方、他部署からの異動や教育によるスキルアップによって対応できる場合もあります。このプロセスで、人材確保が必要なのか、異動や人材育成が有効なのかを判断します。
3.適切な人員計画を立てる
具体的な人員計画を立てるプロセスです。現状と目標の差異を埋める具体的な計画を策定しましょう。主な方向性は以下の2通りです。
- 人材を新たに採用する
- 自社内の異動や教育で対応する
ただし、本人の意志に反する異動は望ましくありません。適材適所は重要ですが、人材管理では社員側の視点を意識する必要があります。企業側の都合を一方的に押し付けると、モチベーションやエンゲージメントの低下、離職率アップを招きかねません。
4.配置転換・育成計画・新規採用計画の実行
配置転換、育成、新規採用などの人員計画を実行するプロセスです。優先度と効果が高い計画から取り掛かりましょう。複数の目標を同時に達成しようとすると、社員の混乱を招く場合もあります。
新規採用では、多様な人材の確保を意識しましょう。先が見えない社会情勢の変化に対応するためには、多様性が重要です。配置転換では社内公募制度、育成計画ではOJT(実務研修)やOFF-JT(実務外研修)、eラーニングの活用も検討しましょう。
5.各プロセスへの適切なフィードバック
評価と改善のプロセスです。人員計画の実施によって目標がどの程度達成できたのかを評価し、フィードバックを実施します。さらに、計画の問題点を洗い出して改善し、再度サイクルを回します。プロセスを1度実行すれば、最適な人材管理を実現できるわけではない点に注意しましょう。
社員にフィードバックする際には、エンゲージメントやモチベーションの低下を招かない方法を取る必要があります。社員自身が主体的に課題を捉えて、積極的に改革に取り組める企業風土づくりも重要です。
人材管理における4つの課題
変化の激しい経営環境の中で企業が人材を的確に活用するためには、人材管理のあり方を見直すことが求められています。この章では、現代の人材管理における課題について解説します。課題を適切に捉えて対策を講じることが、優秀な人材の確保・定着、さらには組織の競争力強化につながります。
多様化への対応
働き方や価値観が多様化する中で、誰もが働きやすい柔軟な組織体制の構築が求められています。リモートワークや時短勤務など、ライフステージに応じた働き方を可能にする制度を整えることで、多様な人材の活躍を促進できます。同時に、成果やプロセスなどを多角的に評価できる柔軟な制度も必要です。一律の基準ではなく、それぞれの働き方に応じた公正な評価を行うことで多様性を強みに変え、組織全体の力を高めることができます。
職場環境・待遇の向上
社員のモチベーションやエンゲージメントを高め、維持していくためには働きやすい職場環境と納得感のある待遇の整備が欠かせません。職場に安心感や快適さがなければ、能力があってもパフォーマンスを発揮しづらく、離職リスクも高まります。具体的には、以下の点を重視しましょう。
- 業務負荷の適正化
- ハラスメント防止
- 風通しのよい人間関係
- 適切な労働時間管理
- 報酬制度
- 福利厚生
働きやすさは一時的な満足ではなく、社員の持続的な活躍と企業の安定成長を支える基盤です。
個人視点の取り組み
人材管理においては企業側の視点だけでなく、社員一人ひとりのキャリア意識を尊重する「個人視点」の取り組みも重要です。終身雇用が当たり前でなくなった今、自立的なキャリア構築を支援する仕組みが求められています。定期的なキャリア面談やスキル開発の機会提供を通じて、自身の「目標」や「成長」を社員自身が考えて行動できる環境を整えることが大切です。このような取り組みは社員のエンゲージメント向上につながるだけでなく、結果的に組織全体の活性化や人材の定着にも寄与します。
情報管理
効果的な人材管理を行うためには、以下の情報を正確かつ一元的に把握する必要があります。
- スキル
- 資格
- 実績
- 評価
上記の情報を把握することで誰がどの分野に強みを持ち、どのような成果を上げているのかが可視化され、客観的な人材活用や配置判断が可能になります。人材データを適切に管理することで、プロジェクトへの最適な人選やスキルギャップの特定など人事戦略に直結した迅速な判断が可能です。また評価や報酬、さらにはキャリア支援にも一貫性が生まれて社員の納得感も高まります。情報管理はタレントマネジメントシステムなどのITツールを活用することで、より効率的かつ正確に運用できます。
人材管理システムを導入するメリット3選
近年、多様な働き方や人材活用の高度化が進む中で、人事業務の複雑さや煩雑さはますます増しています。人事業務の課題を解決し、戦略的な人材マネジメントを実現する手段として注目されているのが「人材管理システム」の導入です。人材管理システムは単なる業務の効率化にとどまらず、組織の成長を支える重要なインフラとなり得るでしょう。この章では、人材管理システム導入で得られるメリットを解説します。
人材管理を効率化できる
人材管理システムを導入することで、煩雑な人事業務を効率化できるメリットがあります。勤怠管理や給与計算など人材に関する多様な情報を一元的に管理することで、手作業や属人的な対応が減り、業務の正確性とスピードが大幅に向上します。さらに社員一人ひとりのスキルや保有資格・過去の評価データなどを蓄積・可視化できるため、人材の全体像をリアルタイムに把握することが可能です。
企業の戦略やプロジェクトのニーズに応じて最適な人材を迅速に見つけ、的確に配置・育成する「戦略的人材活用」が実現できます。人材管理システムの導入は人事部門の業務負担を軽減すると同時に、社員の可能性を最大限に引き出す仕組み作りに貢献します。
従業員のモチベーションアップにつながる
人材管理システムを導入することで、社員一人ひとりの実績や日々の勤務状況などが正確に可視化されます。正確なデータにより、感覚や主観に頼らない公正な評価が可能です。実績や能力に見合った評価を受けられる環境が整えば、社員のモチベーションは自然と高まります。「努力すれば評価される」「成果を出せば正当に報われる」という信頼感が、前向きな行動につながるからです。人材管理を通じて「見える化」された実績と適正な評価が社員の働く意欲を引き出し、組織の成長を支える原動力となります。
市場での競争力を高められる
人材管理システムの活用によって、社員のスキルや成果に応じた適正な評価が可能になると「自分は正当に評価されている」という安心感が生まれます。正当な評価は社員満足度の向上につながり、仕事に対するモチベーションや責任感が高まります。結果として社員はより高いパフォーマンスを発揮し、質の高いサービスや製品の提供が可能です。社員一人ひとりの力が引き出されることで、組織全体の創造力や対応力も強化され、同業他社との差別化が実現しやすくなるでしょう。高度な人材活用と社員満足の両立は製品・サービスの品質向上や顧客満足度の向上に直結し、市場でのシェア拡大や競争優位性の確保にもつながります。
人材管理システム選びのポイント4選
使いやすさ
人材管理システムを選ぶ際は「誰でも迷わず操作できるか」が重要です。マニュアルを見なくても次に何をすればいいかが分かる画面設計やシンプルな操作性は、現場のストレスを大幅に減らします。画面の分かりやすさや動作のスムーズさは資料だけでは判断できないため、導入前にはデモ画面や無料トライアルで実際に操作しておくと良いでしょう。システムの定着率や業務効率を高めるためにも、使いやすいかどうかを必ず確認しておくことが大切です。
システムの柔軟性
人材管理システム導入後に「このような機能が欲しい」「自社の運用にもう少し合わせたい」など、細かなニーズが出てくることもあるでしょう。導入後に必要な機能を追加したり、設定を柔軟に変更したりできるカスタマイズ性は重要なポイントです。業務フローの変化や組織の拡大に対応できる柔軟なシステムであれば使い続ける中での無理や不満が減り、長期的な運用がしやすくなります。導入前に、システム変更時の費用や可能な範囲などカスタマイズ性を確認しておくと安心です。
サポート体制の充実度
人材管理システムの導入・運用において、サポート体制の充実度は重要な判断基準です。導入初期の設定支援や運用中のシステムトラブル発生時に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは業務への影響を大きく左右します。専任担当者の有無や対応可能な時間帯など、事前にサポート体制の充実度を確認しておくと安心です。導入後の運用支援体制がどこまで整備されているかを事前に確認することで、安定的かつ継続的な活用が実現しやすくなります。
外部ツールとの連携可否
人材管理システムの選定においては、既存の業務システムやクラウドサービスとのデータ連携の可否も重要な検討ポイントです。すでに利用している勤怠管理や給与計算などの外部ツールと連携できることで、システム導入時の設定・移行の負担を大幅に軽減できます。また複数システム間で同じ情報を重複して入力・更新する必要がなくなり、人的ミスの防止と業務工数の削減にもつながります。連携性の高さは単体の機能性だけでなく、業務全体の最適化や将来的なシステム拡張への柔軟な対応が可能です。
人材管理を効率的に行うHR Techとは
HR Techとは、Human Resource(人材)とTechnology(科学技術)を組み合わせた造語です。採用、教育、評価などの人材管理に、クラウド、人工知能、ビッグデータ解析などのICT(情報通信技術)を活用することを意味します。
人手不足が深刻化する日本では、HR Techに注目する企業が増えています。人材確保や人事業務の効率化に、HR Techが役立つと考えられているためです。アメリカをはじめとする世界でも優秀な人材の確保が課題となっており、HR Techに大きな関心が寄せられています。
まとめ
人材管理とは、経営戦略の目標実現のために社内の人材を有効に管理・活用する方法です。大量の情報を扱う必要がある人材管理には、HR Techが欠かせません。
タレントマネジメントシステム「タレントパレット」は、データに基づいた施策が可能になる人事プラットフォームです。1つのツールで人材データの一元管理・分析ができ、人事施策のPDCAを見える化できます。
人材管理に関心がある方は、下記の無料ガイドを請求してみてください。
人事情報を一元化し社員を見える化する